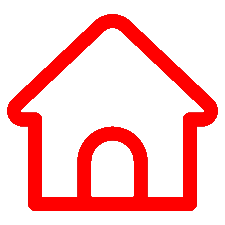青森高校 Infinitelligence
2024あおもり創造学関連生�徒研究テーマ一覧
■アオチャリ・プロジェクト
青森市には『あおもりまちなかレンタサイクル事業』というものがあることを知っているだろうか。私たちはこの事業をより普及し、盛り上げるために事業元である青森市中心市街地活性化協議会さんと協力し様々な活動を行った。どうしてこの事業に目をつけたのか。どのような検証を行ったのか。そもそもシェアサイクルとは?最後にはこれから実験を進める皆さんへのメッセージもあるため、是非これらに注目して発表を見て欲しい。
■サッカーグラウンドの整備
青森高校のサッカーグラウンドは状態がかなり悪く、部活動中の安全面も懸念される。そこで私たちは、どのような整備をすれば現在のグラウンド状況を改善できるかを考え、実験を進めた。まず、水はけの悪さを改善するための方法を過去の類似研究をもとに実験をすると、土の大きさを均一にすると水はけが良くなることが確認できた。その状態を作るために、実際にグラウンド整備を行った結果、より効率の良い整備方法は、ブラシを活用することであると分かった。
■親子で投票に行こう!
私たちは若者の政治的無関心を調査する中で、親の投票に同行した経験がある人々が、投票権を取得後に投票に行く割合が高いという調査結果があることを発見しました。現在「18歳未満の子どもは親の投票に同行できる」ということを知らない人や、親子で投票に行く機会がない人が多いと考えられます。そのため、親子で投票に行くことを促進する方法を考えました。
■#Let’s wear!~自転車ヘルメット着用率向上~
令和5年に自転車ヘルメットは努力義務化されましたが、全国の着用率は約17%と決して高い数字とは言えません。私たちの調査では、本校生徒の着用率は4.2%と全国平均をさらに下回る結果となっています。そこで、自転車ヘルメットの着用促進のために私たちは活動を進めてきました。「みんなが被れば自分も被る」という青高生のリアルな声を参考にして行った活動の実態を皆さんに詳しく説明します!
■脳トレで攻略!
現代の日本では急速に高齢化が進み、それに伴うさまざまな問題が増えている。特に青森県では、健康面での課題が多く挙げられている。これを受けて、私たちは高齢者の健康を支えるための調査や実験を始めた。具体的には、高齢者施設を訪問して情報を集め、調査を行った上で、脳トレを活用して生活習慣の改善に取り組むことにした。身近な中年層、高齢者、高校生にも協力してもらい、私たちが作った脳トレを一定期間毎日解いてもらう形で実験を進めた。
■りんごの皮を第一歩に!食品ロス削減への道
私たちは青森県産特産品の活性化を活動理念と定めて活動を行ってきました。当初は嶽きみのPR活動を考えていましたが、実地調査から市場の飽和状態を認識し、断念しました。そこで、青森県を代表するりんごに着目し、特に食品ロス削減の観点から、廃棄されがちな皮の活用に焦点を当てました。ジャムやチップスなど、りんごの皮を使った新たな活用法を通じて、りんごの魅力再発見を目指し、活動をしてきました。今回の発表では主にその活用法を取り上げます。
■身体能力とFFMの相関性
最近筋トレを行っている人口が増えてきていて、それに伴い、増量を行う人も増えているのではないかと考えた。しかし、インターネットには間違った情報も多数存在し、間違った増量に健康や身体能力に害を与えているという講演を聞いた。そこで私たちは、実際にどのような増量が好ましいか調べ、身体を張って研究した。
■青高オワコン避難所回避ルート
私たちは青森高校の避難所としての機能の実態について調査•実験を行いました。実際、避難所として青森高校が運営されるときの青森高校の重大な問題点を見つけ、まわりの筒井小学校、筒井中学校などの避難施設と役割を比較し検証して、私たちが本当に災害の危機に瀕している時どんな行動をとればよいか、医療的に避難者のQOLを上げるための取り組みについて考えました。私たちが調査を進めていく中でのぶつかった課題や、見つかった新しい疑問についても逐一掘り下げて考察を深めることができました。
■ツボ推し
避難所などでは、運動量が減り気分も沈みやすくなります。しかし、運動することでリフレッシュになるのではないかと私たちは考えました。そこで、私たちの班では、避難所などの狭いスペースでもできる簡単なストレッチや、ツボなどをまとめ、パンフレットを作り、周りの人々に協力してもらい実践しました。
■避難所でのエコノミークラス症候群
災害時は避難した後でも命を落とす危険性があります。避難所などの狭い空間で長時間同じ体勢でいることで発症する、エコノミークラス症候群もそのひとつです。エコノミークラス症候群は、脚にできた血栓が肺に詰まることで呼吸障害を引き起こし最悪死に至る恐ろしい病気です。予防するには定期的に身体を動かすことが挙げられますが、私たちはその対策方法がサイトによってばらばらであることに着目し、どのように身体を動かすのが一番効果的であるかを実験を行って調べました。
■小学生の大人のいない時の避難行動について
小学校で行われている避難訓練は、先生や送迎する場合には親など、大人がいる前提のものであるため、1人もしくは小学生しかいない場合、適切な避難行動ができないのではないかと考え、それをできるようにするテーマの研究。小学生たちと一緒に避難訓練を実際に行うのは相手方の小学校のスケジュールを大幅に変更してしまうため、3年生を対象に講演を実施、実施後にアンケートをとり、その講演が今回のテーマに沿ったものになっているか調査した。
■青高で迷う人を減らそう
あなたは青森高校内で迷ったことはありますか?1度は皆さん迷ったことがあるはずです。特に、新年度の開始時や文化祭の日になると、迷っている人が多く見受けられます。私たちQE15班は、構造が複雑で迷う人が続出している青森高校で、迷子を減らすことを課題に活動を行いました。迷ったことがある人、共感を覚えた人は是非、私たちの発表を見に来てください!
■教室から始める避難のすヽめ
私たちQE16班では教室から出たあとの避難ではなく教室内でのスムーズな避難について探究学習を行いました。教室が狭い!と多くの人が考えており、避難の時に支障をきたしてしまうのではないかという動機でこの探究を行いました。移動スペースを多く確保できるように文系の人たちに協力をしてもらい実験をして結果をまとめました。完璧な発表ではありませんが興味のある人は覗いてみてください。
■あおもり藍の認知度向上に向けて
皆さんは、藍にどんな効果があるのか知っていますか? 青森県ではさまざまな産業が盛んですが、その中でも私たちは「あおもり藍」に着目し、調査、PR活動を行ってきました。製品の企画や販売などを担当しているあおもり藍産業株式会社様に協力していただき、校内でのポスター掲示とSNSによる広報活動に取り組みました。今回の研究発表会を通じて、あおもり藍の良いところを知っていただくきっかけになれば幸いです。
■災害時のライフハック 〜あなたはどれくらい知ってる?〜
自分たちQE18班は青森市で大規模な大雨、またそれに伴う洪水が発生した場合に自分たちの命を守るために必要な知識・行動をクイズ形式で発表していきます。青森市は大雨による大きな被害はここ数十年少ないですが、油断はできません。幼少期から今まで避難訓練や防災教育などを受けてきて災害に対する基本的な知識はあると思います。そんなみなさんも案外知らないような水害の恐ろしさや、役に立つ知識をクイズで学んでほしいと思います。
■留学生のゴミの分別について
留学生がごみの分別で困っていることを知り、私たちは特にリサイクルマークと、捨てるまでにいくつかの過程があるペットボトルなどのごみの捨て方に焦点を当てて調べました。青森中央学院大学の留学生の方々に協力してもらってアンケートを実施すると、多くの人が理解出来ていないことが検証されました。そこで、彼らに特化したルールブックを作成し、そのルールブックを見ながら再度アンケートに答えてもらうと、理解度が大幅に上がりました。
■Reproducing foreign spices with Japanese ingredients
私達の班では、外国の調味料、特にベトナムの調味料を日本の食材で再現する、といった目標で探究をしました。「在日外国人は母国料理を恋しく思っている」という課題のもと、技能実習生へのインタビューや私たちの作った調味料レシピの発信を通して、在日ベトナム人の方が母国の味をいつでも食べれるよう、考えて取り組みました。
■ムスリムフレンドリー
青森にもイスラム教を信仰する「ムスリム」がいます。みなさんは、ムスリムが青森でどんな状況に置かれているか、どういう理由でどんなルールを守って生活しているのか知っていますか?もし明日からムスリムがクラスメイトの1人になったら… 研究に協力してくれたムスリムの女の子の話を交えながら、「ムスリムのリアル」紹介しちゃいます!
■How to eliminate the language barriers at hospitals
青森に住む外国人は病院へ行った時に症状を日本語でうまく伝えられないという問題を抱えています。そこで、私たちは病院で症状を表す時に使われる「オノマトペ」に着目して、体の状況を伝える日本語特有の表現を外国人に教えることができたら、言語の壁が取り除かれると考え、その効果を青森中央学院大学の留学生に協力してもらって立証しました。
■介護施設で働く外国人労働者が抱える津軽弁の問題
介護施設で働く外国人労働者は、入居者の津軽弁の理解が難しいのではないかという仮説のもと、研究を進めました。この仮説は外国人労働者へのアンケートに基づいており、私たちは文化、語彙、日本語の表現の3つの観点からマニュアルを作成しました。外国人労働者が勤務中の会話において意思疎通に問題があった回数をマニュアル使用の前後で比較し、検証しました。結果として、津軽弁よりも同音意義語といった日本語に問題があることがわかりました。この結果から、外国人労働者にとっての音と漢字の関連について新たな疑問が生まれました。
■Remake gyosaicenter for foreign people
青森市で海外の方が一番訪れるフードショップ魚菜センター。しかし、調査してみたところ海外の方がたくさん訪れるが海外の方のための説明やシステムが少ないことがわかった。そこで外国人の方にもわかりやすいように魚菜センターをより使いやすく、よりいい場所にしようと考えこの活動を開始した。最初は魚菜センターに海外の方のためのアンケートを設置させていただき、どこが使いにくくポイントなのか調べた。そこで上がったいくつかの問題点を解決していき魚菜センターの方々とより使いやすい魚菜センターを目指した。
■Disaster prevention
青森県在留外国人は日本での災害時、言語など様々な面から避難が難しいのではないかと考えた。具体的にどのように困るのかを知るため青森県観光国際交流機構に訪れたところ、青森県在留外国人はベトナム人が最も多く、さらに技能実習生の割合が大きいと知った。このことから技能実習生が多く働いている工藤パンの技能実習生に防災意識に関する調査を行った。
■防災ポーチを持ち歩こう!
突然ですが、みなさんは災害対策をしていますか?ご存知のとおり、日本は世界のなかでも自然災害が多い国です。非常用持ち出し袋の用意や、ローリングストック法での食料の備蓄など、しっかり対策をしていることかと思います。ですが、これらの対策は「家にいる」ことが前提となっているもの。外出先で被災した場合の対策は十分にできているでしょうか。自然災害はいつどこで起こるか分かりません。「防災ポーチ」で安心を持ち歩きませんか?
■伝統工芸品に興味を持ってもらうには
青森市では現状として伝統工芸品の良さを伝える機会が少なく、青森市民も外国人の方も伝統工芸品について知らない人が多いため、伝統工芸品の売れ行きが伸び悩んでいます。伝統工芸品の売り上げが上がらない理由は制作工程の手間や工芸品を作ることの難しさ、作品それぞれの唯一無二の魅力を理解してもらえていないからだと予想しました。青森の伝統工芸品について詳しく外国の方に知ってもらう活動を通して分かったことや、成果、行なった活動を通しての考察などを発表します。
■Japanese Food for Foreigners
Do you like Japanese food? I think most people would answer “yes.” Japanese cuisine is loved worldwide for its delicious flavors, unique presentation, and health benefits. With this in mind, our group has been working on promoting the appeal of Japanese food to people overseas. From the start, we conducted a questionnaire to investigate foreigners’ awareness and impressions of Japanese food. The results showed that most foreigners not only enjoy Japanese dishes but also have a strong interest in trying to cook them themselves. Using this valuable information, we collaborated with foreign university students in our prefecture as well as students at Singapore University to create a Japanese food recipe website specifically for international audiences. The site provides easy-to-follow recipes, tips, and cultural insights to help users better understand and enjoy Japanese cuisine. We continuously update and improve the website by incorporating feedback from its users. By doing so, we aim to make the site more user-friendly and informative for people around the world. We hope that our efforts will encourage more people to explore Japanese food and culture. Moving forward, we are committed to further popularizing the site and spreading the joy of Japanese cuisine to an even wider audience.
■菌を撲滅する手洗い
私たちが研究したのは『最強の手洗い』についてだ。コロナウイルスが流行し、約4年が経ち、感染は止まらず今年7月1日から9月30日の期間で第7波が来たとされている。そこで私たちは手洗いに注目し研究した。厚生労働省が推奨している手洗いの仕方が一番菌や汚れが落ちると考え、手洗いチェッカーを利用して水のみで洗った時、石鹸を利用し自己流で洗った時、厚生労働省が推奨した洗い方で洗った時の3つの洗い方を時間を変化させて調べた。実験の結果、厚生労働省の洗い方が最も汚れが取れているとわかった。さらに、汚れの落ち具合を可視化するため、パンでの培養をした。
■夏の冷房の最適解
昨年度は気温がとても高く、家庭の電気代が高かったことに加えて暑さによる不快さを感じた。私たちはエアコンと他の器具を組み合わせて使うことで電気代を抑えられ、かつ快適に過ごせるのではと考えた。そこで電気代は室内の湿度が下がるまでの時間を計測することで、快適さは不快指数を計算することで比較できると考えた。断言はできないがエアコンと凍らせたペットボトルを組み合わせて使うことで電気代を抑えられる可能性が高い。
■減塩と出汁について
青森県の塩分摂取率が高いという課題に着目し、減塩について研究することにした。解決策として出汁活が有名だが、出汁活が本当に有効な方法なのかという疑問が出たので、出汁について実験した。出汁の量を一定にして味噌の量を変え、塩分濃度が低い味噌汁でも美味しさを保てるのかを検証。約70人にアンケートをとり、データを得た。実験結果から、美味しさを保ったまま推奨されている塩分濃度よりも低くすることができることがわかった。よって出汁を使うことで効果的な減塩を行うことができると言えることがわかる。
■塗り絵で高まる集中力
私たちの班は今日生じているスマホの使用による集中力低下の問題を解決するために、前頭前野の働きの活性化の促進を期待できる塗り絵を活用し、探求を行った。塗り絵の有無、塗り絵をする時間を変え、その後計算問題を解いてもらい、計算問題の正答率、解答数、そして計算中の瞬きの回数を総合的に考察した。結果、正答率、解答数を見ると集中力が上がったとは言えないが、瞬きのみに着目すると塗り絵と集中力には関係があるということが考察できた。
■紫外線が人体に及ぼす影響
私たちの身近にあり健康に影響を与えるものとして「紫外線」が挙げられます。紫外線は浴びすぎると皮膚がんになったり、逆に浴びないと精神状態が悪化したりします。そこで、日焼け止めや服の色の違いなどで私たちが受ける影響を減らせるのではないかと考えました。紫外線で色が変わるビーズを用いり、天気や実験道具の種類を変え検証を行いました。紫外線のメリット・デメリット、実験の結果から考察したことや今後の対策などを発表します。
■眠眠打破
ご飯を分けて食べれば、午後の授業で眠くならないのではないか。お昼ご飯を食べて急激に血糖値が上昇し、眠くなってしまうのをご飯を分け軽食をとることによって改善したい。
■青高生の睡眠を改善する秘訣
青高生は勉強や部活で、睡眠時間を取るのが難しいのではないかと思います。そこで、GH7班では、睡眠時間ではなく、睡眠の質を良くすることで日中の疲れを軽減できるのではないかと考えました。生活習慣という観点から睡眠の質について調査し、なるべく日常生活の中で継続しやすいものを取り入れ、睡眠の質が向上するか調べました。
■色と血圧・脈拍の関係とは
生活の中における色の影響に関心を持つようになった。そこで、色と血圧・脈拍の関係を調べることで、生活の中により過ごしやすい環境を作れるのではないかと考え、2つの検証を行った。1つ目は色付きセロハンを使い、運動前後の色が与える血圧・脈拍の変化と勉強との関係性を知るため11人の生徒を対象に行った。2つ目は一般的な色のイメージと検証1の結果が相関しているか確かめるため、全校生徒を対象にClassiでアンケートを行った。
■人類 × 運動 × 音楽=?
運動部必見!!! 探究課題を探す中で僕たちは音楽と運動にはどのような関係があるのかについて興味が湧き湧きました。そのため僕たちはバスケットボールのフリースローを用いて音楽と運動の関係について調べました。運動部の人はこれからの部活動でとても参考にできるような凄まじい結果が得られたので少しでもこの探究課題に興味のある方々はぜひご参加ください!
■バナナの皮を美味しく食べる方法
私たちはバナナの皮を食べやすくするためにバナナの皮の調理法について研究した。現在環境問題の原因として食品廃棄が問題となっており、日本でも大量の食品が捨てられている。そのうち果物の皮の廃棄が高い割合を占めており、さらにバナナの皮が最も多く捨てられていることがわかった。そこで、バナナの皮の調理についていくつかの実験を行った。実験の結果、バナナの皮を24時間凍らせるのと芋けんぴの作り方を真似て加工するのが好ましい食べ方だとわかった。このことから、バナナの皮を食べやすくするためにはお菓子の作り方を真似るのが好ましいと考えられる。
■アイススラリーの可能性
熱中症対策として飲料に着目し、アイススラリーについて研究しました。アイススラリーとは、固体と液体が混ざった状態の飲料です。通常の飲料と比べて、深部体温を低下させるという特徴を持っていますが、入手のしにくさがデメリットです。そこで、アイススラリーを自作できれば、より良い熱中症対策になるのではないかという仮説のもと作成と使用のしやすさという観点を元に実験を行いました。
■日付と生徒が指名される関係性
皆さんは授業中、突然先生に指名されて頭が真っ白になってしまったという経験をしたことはありませんか?実際に、班員自身やその友達も同じような経験をしたことがあるという話を聞いたことがあります。私たちはそうなることを防ぐために、「日付によって生徒が指名される確率が変わるのではないか」という仮説を立てて、研究を進めていきました。
■ロッカーの整理整頓の成績の相関関係
ロッカーが綺麗にしろ、整理整頓しろ、とよく先生に言われた記憶がありませんか?本研究ではそのことについて調査してみました。まず、綺麗さとは何かを定義するために、参考書類の角度とまとまり具合、体積的な占有率を数値的に表し評価することにしました。また成績は一概に定義することが難しいため、論理的思考回路の測定できるような教科、その中でも論理問題、物理、論理回路が適すると考え、これらのテストを作成しました。
■避難経路の見直し
学校にいるときに災害が起こった場合、いかに早く避難できるかに私たちの命は左右される。そこで私たちは、青森高校の避難経路に着目し、セルオートマトンという方法を使った避難時の状況の可視化、様々な避難経路の施行・比較をもとに避難にかかる時間を短縮することを目標に探究活動を進めた。その結果、並び方を工夫することで混雑の解消を期待できることがわかった。この探究をもとにし、避難経路以外の様々な状況にも応用させていきたい。
■ダンボールの可能性ー防災グッズの再現ー
私たちは、青森高校に備蓄されている防災グッズが不足していることを知りました。特に「ダンボールベット」に着目しました。「ダンボールベット」は市販で売っていますが、セットを買うのにはお金がかかってしまうので、私たち自身で防災グッズを作れないかと考えるようになりました。まず、ダンボールベッドのミニチュア模型を作成しました。この模型を使って、耐荷重テストを行いました。その結果、ダンボールベッドが実際に使用可能かどうかを確認しました。テストの結果を基にデザインや強度を改善し、より実用的なベッドの制作できるのかを考えました。
■カラオケで点数を伸ばすには
「数字」に関連させた結果、カラオケの点数に着目して、「カラオケの点数を伸ばしたい」というテーマに辿り着きました。喉の状態(うるおいなど)を良くすることで歌を上手く歌えると考えたので、「喉に優しい食材を食べれば、簡単に早く点数をのばすことができるのではないか」という仮説をたてました。そして、食材を食べる前と食べた後で点数を比較して、何の食材が最も点数の上昇率が良いかを調べ上げました。
■机周りが汚いのは習慣のせい?
机周りの汚さと習慣の因果関係を調べる実験の概要をスライドを交えて発表する。発表内容である実験は、・周りの習慣と関係する質問をして相関関係を調べる ・汚い机の持ち主二人を用意し、1人は綺麗にさせ、もう1人は放置し、習慣による机周りの綺麗さの変化を調査する。のおおよそ2つである。詳しくは、自分たちで「汚さ」を定義し、その定義に当てはまる人を「机が汚い人」とし、逆にその定義に当てはまらない人を「机が綺麗な人」とし、被験者とする。
■授業中の眠気
授業中に学生誰しもが抱える問題……それは眠気が襲ってくること。皆さんも眠気と葛藤した経験があるでしょう。我々はそんな眠気に着眼し、どのような状況で眠気が襲ってくるのか、それに対する対策はどうすれば良いのかについて考えることにしました。まず、現状把握のためにデータを収集し、各曜日、時間、科目ごとにまとめ、傾向、原因を掴み、その後対策を練り、実験をして眠気の改善に繋がるか調査しました。ぜひ皆さんの眠気改善のお役に立てれば幸いです。
■傘を刺す角度と耐久性の関連性
私たちの班は、日常で使うことの多い物かつふと壊れてしまいがちな物として傘に着目しました。そこで、傘は風でひっくり返りやすいという課題を見つけたので、傘を壊れにくいかつ雨にも濡れない最適な差す角度を見つけようと考えました。シミュレーションソフトを使って、傘にかかる圧力や雨の降る角度から最適角を探しました。一般的に傘がひっくり返りやすいと言われている条件下では、約55度で雨と風を効率よく防ぐことが分かりました。
■データで見る蚊の習性
データの活用方法について話し合い、予測という観点に焦点を当てた。蚊に焦点を当てた理由としては、蚊はウイルスや病原菌を媒介し、十分な危険性を持ち合わせているため、そうした蚊からの被害を防ぐために実験を行った。私たちの独自の着眼点としては、蚊を捕獲するために様々な方法を用いた。様々な実験の結果、いくつかの習性を得ることができた。今後の課題は、室内の有効な対策へ絞ることにし、実験を通して得た考えをもとに対策を練る段階へと移っていく。
■ボカロ文化の流行と変遷
近年日本国内外で注目を浴びている電子音声を用いた音楽。その中でも、ヤマハが開発した「初音ミク」や、ここ数年の人気曲のボーカルを担うUTAU発祥の「重音テト」などの人工音声による歌唱ソフト、いわゆるVOCALOIDは日本のpopカルチャーの一つとしてその話題性を高めています。そんなVOCALOIDを用いた楽曲群、通称ボカロ曲の今後の変遷を、bpsや使用楽器などの要素に焦点を当てる事で予測していきます。
■昆虫食
本発表では、昆虫食の可能性と課題について研究成果を報告します。世界的な食糧問題や環境負荷軽減を背景に、昆虫食は効率的な生産性や高い栄養価、環境への優しさから注目されています。一方で、見た目や味に対する抵抗感が課題です。コオロギパウダーを使用した煎餅の実験を通じて、タンパク質含有量が増加しても味の評価に大きな変化がないことを確認しました。この研究は、昆虫食が持続可能な未来の食糧として普及する可能性を示唆するものでございます。
■チョークを使って塩害改善
世界全体の塩害の被害は、世界の耕作地の20%にまで及んでおり、今後数十年でより顕著になることが予想されている。私達は塩害の改善を目的とし、身近な日用品であるチョークの炭酸カルシウムの成分に着目し、チョークが酸性土壌のpHを低下させる効果がある効果があるのではないかという仮説を立て、海水入りの土にチョークを入れた時のpHの変化を調べる実験を行った。その結果、チョークが酸性土壌のpHを低下させる働きがあることを裏付けるような結果が得られた。
■生ゴミの活用
私たちはコンポスト(家庭から出た生ごみを土と混ぜて入れることによって,土の中の微生物等の働きにより,たい肥に変える手伝いをする物)を使用した。また、ミミズを入れると分解がより促進されると考えて、ミミズコンポストも使用した。対照実験では黒土を用いた。結果として、ミミズあり(生ゴミあり)、ミミズなし(生ゴミあり)、黒土のみ(生ゴミなし)の順で成長が促進された。これはミミズが生ゴミを食べて、細かくし、表面積を増やすことで、微生物による分解が早まったのではないか。
■集中力を保つために最適な昼食を考える
昼食を食べると眠気を感じ、昼食後の授業に集中できない生徒が多いと思います。そこで私たちは眠気が引き起こされる原因が昼食にあるのではないかと考えました。そして、昼食後の授業でも集中して授業を受けられる最適な昼食を考えることにしました。ビタミン、タンパク質、炭水化物の3つの栄養素に分けて、どの栄養素が1番集中力を保ちやすいのかを実験しました。
■集中力が向上するのは飲料物か固形物か
私たちの班は飲料物と固形物とをそれぞれ摂取した後で、どちらの方が集中力が向上するのかを研究しました。家で学習していたり、長時間学習していたりすると、集中力が途切れてしまう時があると思います。噛むことによって集中力が向上すると仮説し、勉強と勉強の合間に気軽に摂取できる三ツ谷サイダーとグミを用いて、青高生を対象とし、実験しました。
■塩の距離を活用して塩分摂取量を減らす
青森県民の塩分摂取量が多いのには濃い味が好きなどの理由があります。そこで僕たちは、美味しさや味の濃さに変化なく、塩分の量を減らした減塩料理について研究しました。その中で塩の距離といい、塩の付け方によって変わるものがあります。食べ物の表面につけた場合には「塩の距離は近い」、混ぜ込んだものは「塩の距離は遠い」と定義します。それを活用して、味の変化はなく、含まれる塩分を減らした料理を作ろうとしています。
■Let’s ジェスチャー!
「ジェスチャー」を主なテーマにして研究・実験を行い、伝わりやすさ・伝わりにくさの特徴や効果的な表現など探りました。実験の結果、伝わりやすいジェスチャーは単純で全身を使った動きである、逆に細かく複雑なジェスチャーや概念的な内容は伝わりにくいとわかりました。ジェスチャーの特性を理解して適切に使うことの重要性を強調しました。この研究を通じて、日常でのジェスチャーへの意識を高めて欲しいと思います。
■国内で使える幅広い外国人に伝わるマーク
総探を始めた当初は民泊を活性化する方法を研究対象にしていた。しかし、解決には至らないと思い課題と対象を変更した。変更したきっかけは民泊に訪問し取材を行った際に主人の方の発言、ゴミ箱にイラストがあるにも関わらず分別がされづらいと言っていたことだ。このことから日本人と外国人の感性に差があると思った。差についてはアンケートを実施して可視化した。そして、私たちで自作のイラストを作り民泊で実際に使用してもらいその効果を検証する。
■土地改良プロジェクト
世界には砂漠、荒野その他の作物が育ちにくい環境が存在します。日本では農薬による弊害なども問題になっており、食事を支える作物を育てる土壌の問題の解決の目処は立っていません。また、人間社会によって生み出されるゴミによる土壌汚染等の環境問題も国内外問わず深刻です。そこで私たちはそれに対しての小規模ながら解決策を考えました。私たちは様々な資料を読むなかで家庭から生まれる生ゴミ、プラスチックゴミが農業や土壌改善に役立つ事を知り、ダンボールを鉢植えがわりにしそれらを投入した物としていない物でミニトマトを植え成長の過程を観察しました。結果前者に植えたミニトマトが大きく成長しこの方法は有効である事が証明できました。したがって生ゴミとプラスチックゴミは土壌改善に有効であり、農業でも適量の農薬と併行して育成に役立つと結論づけた。
■害虫を肥料へ
私たちE37班は畑を荒らしている害虫について着目しました。私たちはトラップを作り害虫を集めて肥料を作りJWFTという植物を使って自分たちが作った肥料が市販で売っている肥料と比べて市販と同等かそれともそれ以上の効果が得られるかを実験しました。
■最強の傘を作ろう
市販のビニール傘のような手軽な値段の傘はお世辞にも強度が強いとはいえず、豪雨のときなどに簡単に壊れてしまう。そこで我々は身近なもので傘を強化することはできないかと考えた。いくつか案を出し合い、ホームセンターなどで簡単に手に入る針金で傘の骨格を補強した傘、ビニールに穴を空け空気抵抗を減らした傘、普通の傘の3つの耐久性を検証した。
■鳥が糞を落としやすい場所には色が関係しているのではないだろうか
黒い車の方が鳥に糞を落とされやすいと言う先行研究をもとに、糞が落としやすい、落とされにくい色があるのではないかと言う仮説をもとに調査を進めました。青森市内(駅周辺)を中心に、鳥の糞が多く落とされている場所を調べて、鳥害ハザードマップを作るところから始まりました。
■水車を用いてごみ回収
私たちの班は、悪臭や景観の悪さの増幅、ボート部の練習の妨げ等の堤川のゴミ問題を解決を目標としました。海の表層油やマイクロプラスチックの回収をもすることが可能な装置「シービン」に準えて、川の流れを利用し、簡単かつ低コストかつ環境破壊の温床となるような素材を使用せずにゴミを回収することが出来る「水車」の作成をゴミの回収の可能な素材、水車の浮力、水車の回転等の課題に苦戦しながら行いました。
■犬に優しいりーど
自分たちの班は犬が散歩の時につけるリードについて注目しました。犬が付けているものでよく見かけるものは首輪やハーネスがあります。しかし、首輪は引っ張った時に気管を圧迫し、ハーネスも体に負担がかかります。そこでリードの形によって犬にかかる負担が変わるのではないかという仮説を立て犬の負担を減らそうと考えました。ハーネスと考案した「八の字型」で様々な実験を行い、犬に寄り添って最適なリードを研究しました。
■肥料の悪臭対策
近年、家庭菜園が増加しており、それに使用される肥料の悪臭被害が見られています。皆さんも、家庭菜園だけでなく、畑などに近づいた際に悪臭を感じたことがあると思います。悪臭は公害の一つとなっており、我々、E312班はその原因である肥料の悪臭対策について、研究を進めてきました。研究の結果、匂いを消すという観点において、あるものを使用することによって対策が可能だということが明らかになりました。
■Sales original flavored apple pie in the school and shops
青森県の魅力を世界へ広め、青森県の観光促進を目標に、インバウンド、県産品輸出、ブランディングの3分野に別れて活動しています。私たちは六戸町の小向製菓とともに、ゆず、カシス、紅茶、抹茶、もちの5つのオリジナルフレーバーアップルパイを製作しました。学食での校内販売をはじめ、コンビニやお土産屋などで販売し、最終的には海外販売を目指しています。