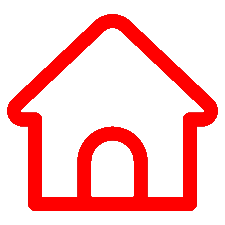2月26日(水)探究型学習発表会が行われ、2年生全員がこれまでの探究学習の成果を発表しました。加えて、SSH事業(国内・海外研修)やSTAGEプログラム海外研修の報告、グローバルパネルディスカッションも同時に行われました。
■午前の部
全体発表(第一体育館)
代表8グループと各種研修報告
■午後の部
分科会発表(教室棟)
全グループによる発表
グローバルパネルディスカッション(使用言語:英語)
参加国:ベトナム・シンガポール・台湾・マレーシア・
日本(一部オンラインを含む)
毎年、研究のレベルアップが見られます。
生徒は課題設定・仮説立案・検証・考察・まとめ・発表の探究学習のステップを繰り返し、研究を深化させています。
研究のレベルは以下のコメントからうかがい知ることができます。
「現代の日本の課題を実際のデータを使って明確に表示していたのが良いと思いました。」
「どれだけ利益が出るのかを計算した上で計画的に実証できているのが良いと思いました。」
「課題である「汚い」の基準をしっかり設定していてわかりやすかった。人の能力や技能が調査の対象になっているため結果を目で見ながらデータ化するのは難しいと思うが、実験になるべく影響が出ないような配慮がされていて良かった。対象者の設定の仕方や実験の方法が良かったと思う。」
「いきなり本実験をするのではなく、小さいモデルを使って仮実験をしていたことが成功への近道だと思った。」
「自分たちで実際の店舗に行き、QRコード付きの紹介パンフを設置できているのが良いと思いました。」
「実験自体は失敗に終わっていたものの、考察に基づき具体的な研究が行えていた。(テストの)点数を落としてしまう原因として、ケアレスミスが挙げられていた。確かにその通りだと思った。」
「国民的キャラクターにも黄金比率が使われているのにすごいと思った。」
「避難時間を短くする、セルオートマトンを使ったシミュレーションでモデル化することで人の動きが分かりやすかった。数学の社会貢献はすばらしい。」
「ベトナム人にフォーカスして、日本の調味料でできる限り本物の味に近づけていて、実際に試しやすくていいと思いました。実際にムスリムの方の声を聞いて課題解決にもっていったところが良かったです。」
「少ない検証回数でも多くの考察ができていると思いました。考察では検証で不十分な部分の分析が詳しく行われていて、良かったと思います。従来の避難経路と新たに考案したものをいろいろな視点から考察しているところもすごい。」
「テンセグリティ構造の存在を初めて知り、実用化まで研究が進めば嬉しいと思った。」
「80日にも及ぶ実験とデータが多く、信憑性が高いと感じわかりやすかったです。」
「シンガポールで直接インタビューをし、また教えたいメニューをウェブサイトとして纏めてるのがいいと思った」
「実際に工藤パンさんに調査に行っていて根拠になっていていいと思いました。」
「様々な避難ルートを想定していてよかった。今学校で定められているルートがなぜそのルートに決まったのかを詳しく知りたい。自分たちで条件を操作し、いろんな角度からアプローチしていてよかった。」
興味・関心の高揚や新たな知識の獲得にも貢献しているようです。
「行われているボランティア活動を知らないことが、人手不足解決に至らない原因だということに納得しました。SNSは多くの高校生が見るものなので、そこで情報を提供するのはとても効率的で良いと思いました。また、この発表でこども食堂のボランティアに興味を持ちました。」
「数学はあらゆることに利用できることを知れた内容だった。」
「外国でも日本と似ているマークが使われていることがわかりました。ピクトグラムを世界的に通用するものに変えることで、外国人観光客も困らなくなると思いました。」
「プラスチックとゴミの土壌が一番育つと言っていてこの2つに植物を育てる性質を初めて知って驚きました」
「目的に沿って実験をできているのが良かった。電気料をしっかり計算してくれたから、下がっているかどうか分かった。結果までの流れがしっかりしていて、実験も仮説に関連していて良かった。結果からの考察もできていたと思う。」
「なんとなく放置していたケアレスミスを丁寧に研究しており、参考になった。」
「自分もボランティアに参加していたが、その背景にあるような人員不足などの課題を今回初めて知れて、よりこども食堂に携わりたいと思うようになった。素敵な取り組みだと思う!」
発表のしかたにもレベルの向上が見られました。
「班の人達みんな英語の発音が聞き取りやすかったです。また、写真や資料がおおく、要点もまとめてあって分かりやすかったです。」
「日中の活動と睡眠潜時の関係に関する具体的な数値が示されていて分かりやすかった。」
「実際に幅広い人を対象に実験を行っていて具体的なデータとして結果が得られていたので説得力がある。」「しっかりとした実体験を交えて話をしていて、説得力があった。」
「美をテーマにしているだけあって、スライドが美しかったです。あとは発表している人の話術がすごかったです。いろいろな困難を乗り越えてきたんだということが分かりました。」
「実際に外部機関に訪問して検証していた点がよかった。備蓄品を見に行きサイズ感や量を確かめていて検証がしっかりしていてよかった。」
「課題に対して検証がはっきりしていて、説明もわかりやすかったところが良かったと思った。」
「スライドで数値を比べることができたので見やすかったです。」
発表者としてはもちろんのこと、聞き手としての批判的精神も養われていることが下記のフィードバックにも表れています。
「集団心理的な理由もあるとおもうので、人の行動をどう変化させられるかもっと色々な方法でアプローチして欲しいと思った。」
「数値をしっかりと調べることで対比や条件がわかりやすくなっていて良いと思ったが、βカロテンの摂取量との相関関係はあるのか。」
「(課題である、上手に歌が歌えるかどうかは)栄養が関係あるという仮説や考察なのにも関わらず、歌う直前に(=体内での消化が始まる前に)食材を摂取していて実験として成り立っていない。それに、歌っていくにつれて上達してしまうのでは?また、『習性』というには行動の数が少なく物足りなく感じました。」
「途中計算の採点の有無の実験について、採点する際に『結果は合っているが過程でミスがある』という場合の過程のミスを考慮しているのでしょうか?説明がなかったのでわかりませんでしたが、仮説と逆の結果になった理由はそこにあると思います。」
「実験に信頼性がない」
「調査対象を増やせばもっと的確な結果が得られそうだと思った。」
「スライド一枚に示している項目が多くて少しわかりにくかった。」
「ガイドブックはなぜ英語などの外国語ではなく日本語で作っていたかが気になりました。」
「外国人にアンケート調査をした部分で、調査元を書いて欲しいと思いました。」
「参加したイベントの詳細を教えて欲しいなと思いました。」
「紹介だけにとどまらず、伝統工芸品を作っているところをリサーチしたり、体験できる場所をまとめた案内をつくるなどがあれば良いと思いました。」
「テーマである『睡眠』と、他の競技との関係も調べたり、被験者数を多くしたりするとなおよいと思った。」
「青森にいる外国人はアジア圏の方が多いとのことでしたが、日本語以外の多言語対応については検討していますか。」
「テーマと内容に違いが生じていたものの、内容はとてもおもしろかった。」
後輩にもよい影響を与えました。
「課題設定の変更時には、臨機応変な対応が重要なのだと分かりました。」
「季節によって検証ができないテーマを選んでしまうと、活動をしづらいということがわかった。検証をする際には、できるだけ多くの人数で検証できるようにし、より正確な結果を得られるようにした方がいいということがわかった。」
「発表の際、事実だけでなく自分たちの経験も伝えているのが良いと思いました。」
「やはりデータを実際に集めることは重要だと思った」
「一回で終わりにせず、何回か行なっていて資料を増やしていていいなと思いました。」
「シミュレーションを使って、天候に左右される実験を別の方法で行なっていてすごいなと思いました。」」
「実験がうまくいかなくても、計画を練り直して実験していて結果が得られていたのですごいと思った。」